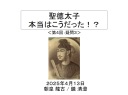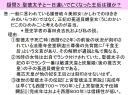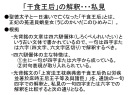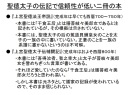●第4回:疑問3
疑問3:聖徳太子と一日違いで亡くなった王后は誰か?
答は、一般に言われている膳菩岐々美郎女(かしわでのほききみのいらつめ)ではなく、正妃の菟道貝蛸皇女(うじのかいだこのひめみこ)と考えるのが妥当です。
これは歴史学者の喜田貞吉氏および私の説です。
理由は次の通りです。
理由の1つ目は、聖徳太子死亡時(西暦622年)の前後の状況が刻印されている法隆寺金堂釈迦三尊像の光背銘に「干食王后」という文言があり、その解釈が通説と私で異なることです。
理由の2つ目は、当時の女性は出自でランク付けされていたことです。聖徳太子の妃の中でランク一番は敏達天皇と炊屋姫(後の推古天皇)の子の菟道貝蛸皇女です。
推古天皇が他の妃を王后とは刻印させないはずです。
理由の3つ目は、後世の聖徳太子の伝記『上宮聖徳法王帝説』(完成年は早くても西暦700~750年)と『上宮聖徳太子伝補闕記』(完成年はおよそ西暦800年)は信頼性が低いことです。
●釈迦三尊像光背銘の一般的釈文
釈迦三尊像光背銘を解釈する時、一般的には添付の画像のように区切られて読まれます。
そこで、「干食王后」が次のように解釈されています。
●「干食王后」の解釈・・・通説
通説では、聖徳太子と一日違いで亡くなった「干食王后」とは、膳菩岐々美郎女(かしわでのほききみのいらつめ)であると解釈されています。
その根拠として次のような論が述べられています。
・ 「干食王后」については、太子の伝記の一つ『上宮聖徳法王帝説』に、膳加多夫古(かしわでかたぶこ)の娘の膳菩岐々美郎女と注記されています。膳氏は天皇家の食膳のことを担当していた豪族です。
・当時、炊事を担当する召使である廝丁(しちょう)のことが「かしわで」と言われていて、木簡に「かしわで」のことが「干食」と書かれているので、光背銘の「干食王后」は膳(かしわで)夫人(菩岐々美郎女)のことです。
・干食は食を干(もと)む、食に干(かか)わるとも解釈できるので、「干食王后」は天皇家の食膳のことを担当していた膳氏出身の膳(かしわで)夫人(菩岐々美郎女)のことです。
という論です。
●「干食王后」の解釈・・・私見
聖徳太子と一日違いで亡くなった「干食王后」とは、正妃の菟道貝蛸皇女(うじのかいだこのひめみこ)である、というのが 私の見解です。
その根拠は次の通りです。
・光背銘の文章は四六駢儷体(しろくべんれいたい)という古い文体で書かれているので、一句は四字または六字(四文字、六文字区切り)で解釈するべきです。
・四六駢儷体の主な特徴は、
①主に一句が四字または六字から成っている。
②対句表現が取り入れられている。
です。
・光背銘文の「上宮法王枕病弗悆干食王后仍以労疾並著於床時王后王子等及與諸臣」を、通説の一句四字での解釈と、私見の一句四字または六字での解釈を比較すると次の通りとなります。
・一句四字の解釈。・・・これが通説となっています
上宮法王。枕病弗悆。
干食王后。仍以労疾。並著於床。
時王后王子等。及與諸臣。
・一句四字または六字の解釈。・・・これは私の見解です
上宮法王枕病。弗悆干食。
王后仍以労疾。並著於床。
時王后王子等。及與諸臣。
・私の見解の方が綺麗に対句表現になっていると思います。
次に通説と私見の両方の読みと解釈を見てみましょう。
・ 通説の読みと解釈
上宮法王。枕病弗悆。
干食王后。仍以労疾。並著於床。
上宮法王は、病に枕し悆(こころよ)からず。
膳夫人(菩岐々美郎女)は、看病疲れで、並んで床についた。
が通説の解釈です。
・私見の読みと解釈
上宮法王枕病。弗悆干食。
王后仍以労疾。並著於床。
上宮法王、病に枕し、悆(こころよ)からず食を干(ほ)す。
王后(菟道貝蛸皇女)は、看病疲れで、並んで床についた。
これが私の読みと解釈ですが、ポイントは「容体が悪くなって食事が摂れなくなった」という解釈です。
●出自ランクによる「王后」の判断
当時の女性は出自でランク付けされていました。
聖徳太子の妃として歴史に残っている人は、
①敏達天皇と推古天皇の娘の菟道貝蛸皇女
②敏達天皇と推古天皇の孫娘の橘大郎女
③大臣・蘇我馬子の娘の刀自古郎女
④臣・膳加多夫古の娘の菩岐々美郎女
の四人で、一番のランクは菟道貝蛸皇女でした。
聖徳太子が亡くなったときには推古天皇も権力者の蘇我馬子も健在だったのだから、我が娘を差し置いて、当時の序列で言うと四番目の妃の菩岐々美郎女のことを「王后」と、聖徳太子と等身の釈迦三尊像の光背に刻印させるはずはありません。
親の気持ち、人情を考えれば、このことは納得して頂けると思います。
●聖徳太子の伝記で信頼性が低い二冊の本
聖徳太子の伝記としてしばしば取り上げられる『上宮聖徳法王帝説』と『上宮聖徳太子伝補闕記』は信頼性が低いです。
『上宮聖徳法王帝説』の完成年は早くても西暦700~750年で、聖徳太子が死んでから約70~120年後に書かれたものです。
・また、本書には「干食王后」とは膳菩岐々美郎女であると注記されていますが、その根拠は示されていません。
・さらに本書には、聖徳太子の后の菟道貝蛸皇女のことを太子の一族の中に書いていません。正妻のことを一族の系譜に書かないというのは不可解です。
『上宮聖徳太子伝補闕記』の完成年はおよそ西暦800年で、聖徳太子が死んでから約170年後に書かれたものです。
・本書には「吾得汝者、我之幸大」と太子が菩岐々美郎女を誉めちぎった言葉が書いてあります。そのため、それほど愛していたのなら「干食王后」は膳菩岐々美郎女だろうと思われ易いのです。
・しかし本書は元ネタとして膳家の記録が使われているので、そのまま信じられません。