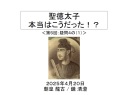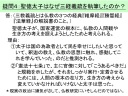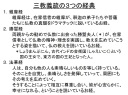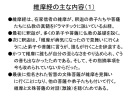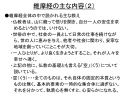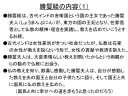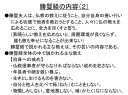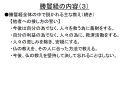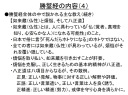●第5回:疑問4の(1)
疑問4:聖徳太子はなぜ三経義疏を執筆したのか?
答は、聖徳太子が、国家運営の根本に、仏教の「人間観や生き方の考え」を据えようとしたためと考えられる、です。
なお、三教義疏とは仏教の3つの経典『維摩経』『勝鬘経』『法華経』の解説書のことです。
理由は次の通りです。
太子は国の為政者として民を幸せにしたいと思っていて、釈迦の教え、仏教の思想に触れ、感動してこれを学んでいった、のだと推測されます。
「憲法十七条」で、主に官僚に対して「こうあるべきだ」と規範を示したが、それをしっかり実行・定着させるためには、人間の根本の在り方、生き方の考えから変えていかなければいけないと太子は思ったのだと推測されます。
現実の政治に嫌気がさして、仏教研究にいそしんだのではありません。
●三経義疏の3つの経典
一般に三経義疏と一括りで呼ばれる『維摩経義疏』『勝鬘経義疏』『法華義疏』のそれぞれが解説している元の経典について概略を見てみましょう。
1.維摩経
維摩経は、在家信者の維摩が、釈迦の弟子たちや菩薩たちに仏教の真髄をドラマチックに説いているお経です。
2.勝鬘経
両親からの勧めで仏教に出会った勝鬘夫人(しょうまんぶにん)が、在家信者として仏教の精神・理念を実践し、教えを広めていこうとする姿を描いて、仏の教えを説いているお経です。
なお、勝鬘夫人は古代インドの舎衛国(しゃえいこく)という国の王女で、東方の国の王妃となった人です。
3.法華経
人は、自分も他の人も素晴らしいものを等しく持っています。
そのことを自覚し、素晴らしさを発揮していって、周囲にもその考えを広めていってください。
そうすることによって相互に尊重し合い、皆が心安らかに、幸せになれるのです、ということを説いているお経です。
仏教はどんな教えかを心から知ろうとする者たちへ贈られる、熱いメッセージと言えるものです。
●維摩経の内容
それでは次にそれぞれの経典の主な内容を見てみます。
維摩経は、在家信者の維摩が、釈迦の弟子たちや菩薩たちに仏教の真髄をドラマチックに説いているお経です。
最初に釈迦が、多くの弟子や菩薩に仏教の基礎を説きます。
次に釈迦は、「維摩が病気になったので見舞いに行くように」と弟子や菩薩に言うのですが、誰もが行くことを辞退します。
かつて維摩に誰もが自分の至らなさをやり込められ、ぐうの音もでなかったためです。
そして、その指摘事項を今も改められていないからでした。
最後に指名された智慧の文殊菩薩が維摩を見舞いに行くことになり、他の菩薩や弟子たちも付いて行きます。
維摩と文殊菩薩の対話(激論)を聴くためです。
維摩経全体の中で説かれる主な教えは次の通りです。
・仏教者は、山に籠って悟りを開き、自分一人の安住を求めるというのでは、いけないのです。
・世俗の中で、社会の一員として日常の仕事を続けながら、世の人に恵みを与え、他者や社会に関わり、安寧な地域を創っていくことこそが大切です。
・一人ひとりが、より良く生きようとすること。それが人々を幸せへ導くのです。
・上記の他に、仏教の基礎とも言える「空」(くう)について説いています。
・空(くう)・・・全てのものは、それ自体の固定的本質というものは無く、基本的要素の一時的な集合体に過ぎないのです。
それを分かって、執着心を無くすと、心安らかになれるのです。
●勝鬘経の内容
勝鬘経は、古代インドの舎衛国(しゃえいこく)という国の王女であった勝鬘夫人(しょうまんぶにん)が、東方の国の王妃となり、在家信者として仏教の精神・理念を実践し、教えを広めていこうとするお経です。
古代インドは女性差別がきつい社会でしたが、仏教は在家の女性が教えを説くという形で、女性の貢献や救済を訴えました。
まず、勝鬘夫人は、大変素晴らしい教えを聞いたからという両親からの勧めで仏教に出会います。
仏の教えを知り、歓喜し感動した勝鬘夫人は、自分が感動した教えを夫の国王と自分の子供たちに語り、そして国王と共に国民に仏の教えを広めていきます。
国民と共に幸せへの道を歩もうと思ったのでしょう。
勝鬘夫人は、仏教の教えに従うこと、自分自身の善い行いによる功徳で他者を救おうとすること、人々に仏の教えを広めることに、全力を尽くすと誓います。
なお、人々に仏の教えを広めることを誓うのは、素晴らしい教えを広めないと、周囲環境が良くならず、誰も彼も幸せになることが出来ないからです。
勝鬘夫人の誓いの内容が勝鬘経で説かれる主な教えです。
勝鬘経全体の中で説かれる主な教えは次の通りです。
【自身への戒め】
・仏教信奉者が守らなければならない戒めを犯しません。
・年長者や師を敬い尊びます。
・生きとし生けるものを害しません。
・自分と他人を比べて妬(ねた)むことをしません。
・物惜しみしません、意地悪しません、頑(かたく)なになりません。
【他者への接し方の誓い】
・今後は自分の為でなく、人々を救う為に蓄財をします。
・自分の利益の為でなく、人々の為に、救済活動をします。
・人々の苦しみを除き、安穏にします。
・仏の教えを、その人に合った方法で教えます。
・今後、仏の教えを堅持して決して忘れることはしません。
【如来蔵(仏性)と煩悩、そして八正道】
・如来蔵(仏性)とは、人に具わっている「仏(覚者。真理を知り、心安らかな人)になれる可能性」のことです。
・日本で俗に言う「死んだらホトケになる」のホトケではありません。
・全ての者には如来蔵(仏性)が具わっているのですが、煩悩がそれを覆い隠しています。
・煩悩を取り払い、如来蔵を引き出すことが肝要です。
・煩悩を克服し、正しく生きるための基本的精神が八正道と言われるものです。
・八正道は八項目からなりますが、その数例を挙げてみます。
正見:正しい見解。物事に対する正しい解釈や評価です。
正語:正しい言葉遣い。正しい言葉は人を良い方向へ誘います。
正精進:正しい精進(努力)。戒律を守り心身を清らかにすることです。